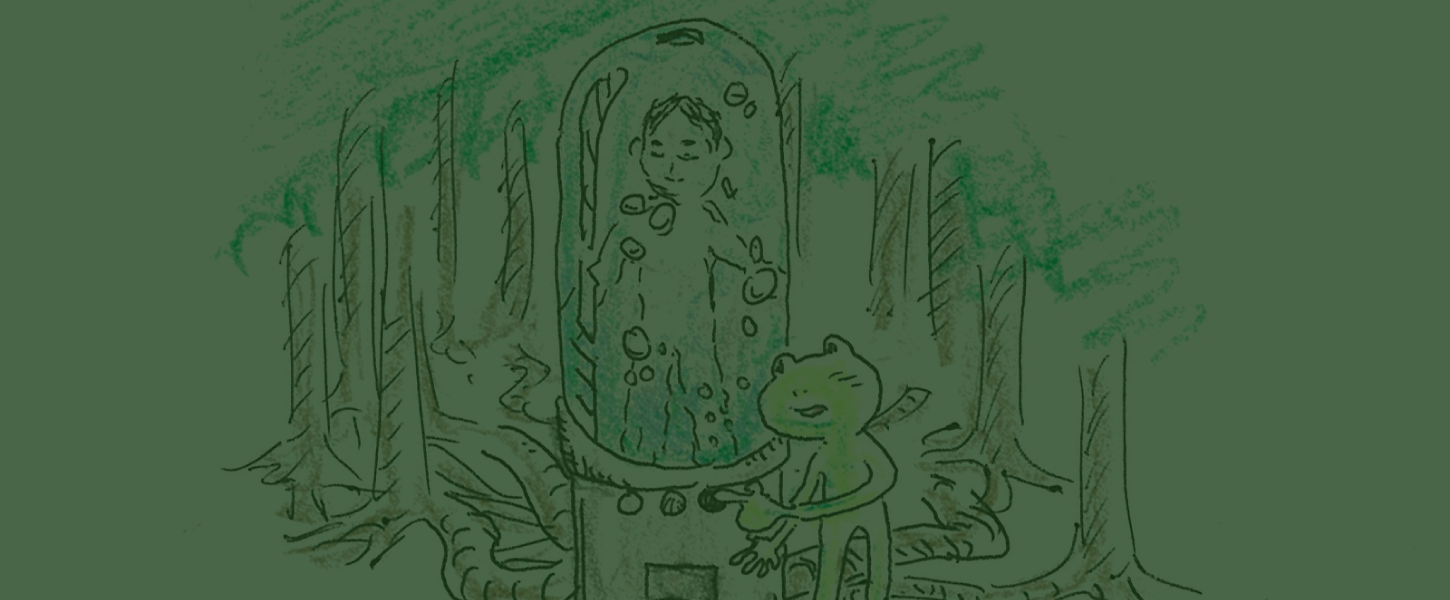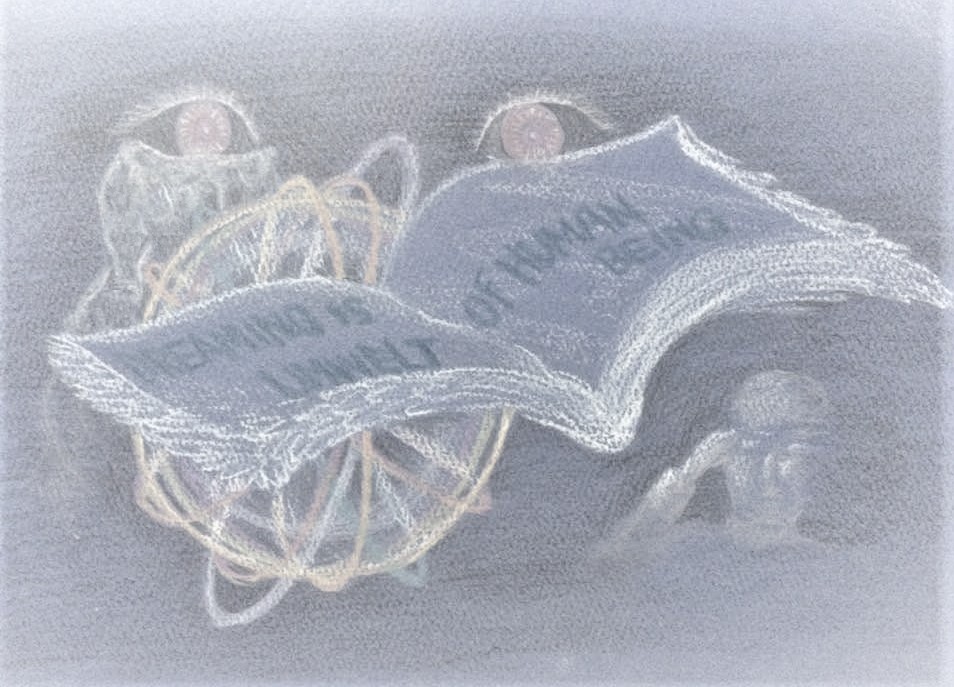
〖第3話〗
* ~ * ~ *
「ねぇ おかあさーん! そろそろテレビ始まるから、いぃい?」
そう言うと私は、夕食の支度の手伝いでテーブルに運んだ箸やご飯茶碗をおそまつに並べてテレビの磁力につかまった。母はちゃんと子供がテレビに囚われの身となる時刻をあらかじめ予定に入れて、私の労働力を必要なポイントに投入してくれているのが分かった。私に手伝えるところはもう今の時点でないという放免の安心感の中、あこがれの世界へとテレビの窓を抜けて入っていった。
「超能力小僧でもあるのか。いやいや そんなぁこと知ったことか。あんなガキの一人や二人に何を恐れているんだ!」
太平洋戦争でアメリカ軍ならぬアリメカ軍が研究していた超能力人間の極秘資料を、これまたなぜか手に入れた日本軍ならぬ月本軍が、少国民を使い、開発して生まれた青年兵の活躍を描いたアニメが、少女時代の私の大好きな番組だった。
戦闘機が、皇紀の下2桁の数字をとって零式や十式と呼ばれた倣いとは違って、彼ら青年兵たちはまったく違う時間軸から産まれたという想いで「新式」と総称され、最新式の兵器として扱われながらも、思春期の恋や厭世感に悩みながら自分たちの身をささげていく姿に、自我が芽生えた頃の私は魅了されていた。
*
小学生の頃、クラスに大好きな男の子がいた。
四年生から五年生に上がり、クラス替えをしたときにその子と席が隣りになって話すようになり、そのうちだんだん意識するようになった。恋心が芽生えそうに感じていた二学期の終わりに、突然その子は一家で転校してしまった。それもアメリカへ。
―アリメカならまだ私だって身近で知ってるのに! ―そんなことも思った。
我が家の経済水準のためか、文化水準のためか、はたまた私がただ単に小さな世界への興味が強かったためか、いずれにしろ私の世界は近くの商店街と公園と、遠くても最寄りの駅までがすべてだった。アメリカというのがこの私の世界と地続きの地球上にあるだなんて、全く想像できなかった。
そんな淡い恋心がきっかけだったと思うが、私は社会に関心を示すようになった。
〝地理的にも歴史的にも、つまり空間的にも時間的にも、この世の中にはたくさんの世界がある〟
私の中でそれが世界認識のひとつの美しい確信として鳴りはじめた。そしてその後の人生を導いていった。
その頃から、新聞の切り抜きコラージュが私のルーチンワークのひとつとなった。毎日のコラムは日替わりで執筆者が替わり、それぞれの人の目を通した世界がそこにあった。私にとって世界は大きくてずっと遠くにあり、直接触ったり分かったり出来るとは到底思えず、こうして何人もの人の視点を借りて色々な角度からのぞかせてもらっていた。
そして週の終わりの日曜日には本の特集ページが楽しみだった。そこには著者たちが見ている世界が一冊の本となって並んでいて、コラムのように垣間見えるだけではなくって、どっぷりと世界に入る入り口のように感じられた。
家のみんなが読み終わったのち、切り取る私の手元に新聞がやって来るのは、晩か翌朝のこと。朝にコラージュしたりすると、そのあと、今日一日の現実の時間は、付け加えられた夢のように感じられた。そして私自身が体験する出来事は、世界という大きな本に記録されることのない夢想のように感じられた。
~ ~ ~
その世界という大きな本の中から、一人の強く静かな女性が私を呼んで語りかけた。
「感覚のどこかで気づいていたかもしれませんね、小春。そう、恋人でした。」
そう言って彼女は静かに立ち上がった。
そのままゆっくりと土間へと進んでいくと、台所の棚から塩壷を取り出してこちらへと戻ってきた。
「笑われてしまうかも知れませんが、大事な形見なため、塩壷に納めております。本当ならば、彼の体の一部をこそ、そばに置いておきたいくらいなのです。命そのものを持っていたいと思うくらいに胸を焦がしておりました。」
そう言い終わると、その女性は壷の中から黒い手帳を取り出して、塩を丁寧にはたき落して私に差し出した。永遠とも感じられたその一瞬間の後、私の手の中に納まったその手帳の重さを、しばらく時間のフィルムを巻き戻すようにして感じていた。ようやくすべて巻き戻ったように感じたとき、表紙を静かに開いていいという許可をもらえたように思え、右手の親指と人差し指で黒い表紙を挟み静かにめくった。
そこには祖父の名前があった。
この手帳の持ち主が祖父に宛てて書いた願いごとが綴られていた。
~ ~ ~
世界という大きな本が、どこからともなくそよいできた風に吹かれて数ページめくれ戻った。
そこから、強い日差しに照らされた白い土の道が現われた。その道は真っ白に光っていた。
道の向こうから人が歩いてきた。
胸の前に箱を抱えて、出迎えてくれた家人にそれを手渡した。
加えて鞄の中から一冊の手帳を取り出し、箱の上に乗せた。
箱を手渡して手ぶらになったその人は、あらためてまっすぐ起立し、両手の五本の指をぴったりつけて足元へと伸ばし、右手を挙げ、自らのこめかみに指先を向けたのち「敬礼!」と大声を上げ、長い間、時間を止めた。
家人たちはようやく家の中に戻り、その重たそうな箱を開けると、中には石ころだけが入っていて、手記の書かれた手帳だけが男の存在がこの世界にあったことを証しするのみだった。何度も何度も読み返した彼の両親は、その最後のページに書かれた願いを叶えてあげるため、住所の書かれた紙片と手帳を彼女に手渡して、ここに住んでいる幼馴染みに持って行って下さいと言った。
真っ白に光る道を彼女はひたすらに進み、しかるべき方に手渡して帰ろうとしたとき、手記を一通り読んだその方は言った。僕を貴女の隣りの空いた席に座らせては貰えませんか、と。それが祖父だった。
~ ~ ~
ほら、小春の世界も、ちゃんと世界という大きな本の中に含まれているじゃないか――そう私の頭の中で聴き覚えのある声が言った。
高校時代に自分でまとめあげたレポートの内容が、その本のページに現れてきた。
祖父は、家の中にさまよう過去の幽霊の面影からただ息をつめて逃げてきたのだろうか。
「あのときもし、私に実力がもっとあったらきっとわしの属した一団を死なせずにすんだのだ! 私一人がただこうして抜け抜けと生き続けてしまった。くそっ。死者の亡霊たちが夜な夜な俺を責めに来るんだ。毎夜毎夜、俺は悪夢にうなされて目が覚める… 眠りに落ちるとはよく言ったものだ。真っ暗な底の見えぬ黒い黒い『眠り』という名の沼に落ちていくような気分なんだ。毎朝かろうじて沼から這い上がるように目を覚ましてこちらの世界に帰って来たときに、あぁ今日も生きて帰ってきた、そう思いながら起き上るんだ。」
これまで家の中での祖父の存在は、まるで透明人間でもあるかのように、どこにもなかった。そんな彼の来歴に初めて触れたのは、高校に入ったのち、歴史の授業と、その先生が顧問をする歴史サークルの活動の一環で始めた、戦争体験の聞き書きの活動を通してだった。
ゆっくりと語る祖父の戦争体験は、時計の針さえも遅くさせるのではないかというくらいに一つ一つ丁寧に語られた。祖父の中ではその体験はすべてでひとかたまりのもので、けれども言葉にするにはある断片を切り取って伝えてくれるから、彼にとってその行為はもどかしさを感じざるを得ないのが手に取るように伝わってきた。また私としても、時系列で語られるのでもなく、主語が一貫してるわけでもないものだから、今これはいつどこの誰の話なのかと戸惑いながら聞き取っていった。
その行為はさながら手毬を祖父がほどきながら、その糸を私がまた毬としてまとめているような風だった。むこうにこっちに回しまとめていく私の手の毬は徐々に形を大きくしていった。反面、祖父の手の中の毬は小さくなり、中心近くの姿が見えてきていた。
しばらく語りが止んでいるとき、私は祖父の左頬のあざを見つめた。そして、戦火の爆風で炎が上がり、その火に焼かれて出来たあざを見ると私はいつも「江戸時代の罪人の入れ墨のようだな」と思った。仲間を死なせた罪で刻まれた刻印のようだったから。
高1の夏から始めたその作業は断続的に進んでいき、徐々に話だけが貯まっていった。そして高3の夏休みへ届こうとしていたけれども、それがまだひとつのまとまりをなしていないように感じられた。
ある梅雨の終わり間近の夜、私はこれまで書きためた話を丁寧に読み返した。夏の虫が待ちきれないとばかりに鳴き合っているのをベランダ越しに聴きながら、祖父の見てきた世界に入っていた。
私の五感はわずかに変化を起こし、この夜がどこまでも静かでどこまでも長く感じられた。
「そうか、今私が感じているこの世界からおじいちゃんの世界を紡いでいけばいいんだ。」
私は虫たちに宣言するかのようにそう言った。
世界になんて、本当には届かない。そうおじいちゃんは言った。
「よし。とにもかくにも、私のこの限定された体と認識から見える世界を愛そう。」
高3の夏の終わりに仕上がった聞き書きの結晶を持って靖国神社へと私は行った。その「仕事」が終わった後、誰かにこのことを報告したい気持ちが膨らんできて、その誰かはやっぱり戦いの死者の方々だよなと思い足を運んだ。私には、鳥居の中において目に見えるものはすべて重々しく映った。
この感覚は何か違うと、私は拒絶するように目を瞑った。
そして〝想像〟の手を前へと持っていき、両手の上に私なりに巻いてまとめあげた手毬を差し出した。これが、私が祖父や祖母から紡いだ記憶の糸で丸めた、記憶の結晶の手毬です。そう心の中で彼らに語りかけた。死者は、優しい面影だけを私の心に広げるのを感じた。
ひとしきり、そうした時間を持ったのち神社を後にした。皇居のお堀を見ながら一周し、そして駅へ向かって帰路についた。
都心の真ん中にああした場所があるんだな、この国は。
その事実をずっと噛みしめながら家にたどり着いた。
こうして結果的に手渡された形となった祖父母らの記憶のおかげか、その後に都心で大学生活を送ることになる私は孤独を感じることがなかった。
中学3年の3学期というタイミングで引っ越すこととなった厄介な家族事情は、その後私にしばらくの間、自分がどこにいるのか分からない迷子にさせた。
そのことと、小学生の時に好きな子がアメリカに行ってしまったこととが火打石となり、私が歴史へ惹かれていく導火線が着火した。一体私は今なぜここにいるのか。この私の中の差し迫った問いへ、しっかり胸を貸してくれ、ぶつかって行かせてくれたのが歴史だった。
高校の歴史の授業が面白かったことも救いだった。その先生が顧問をするサークルに誘われて始めた第二次世界大戦の伝記調査。その中でたどり着いた取材先が祖父母。そしてそこから得ることができたこの手の中の記憶の手毬。それは私に、一体私は今なぜここにいるのかの問いを問い続け、先へと歩みを進めてくれる勇気を与えてくれた。
不思議と、もうどこにいても、ひとり迷子の気持ちになることも孤独を感じることもなくなっていた。
(第3話/全10話)