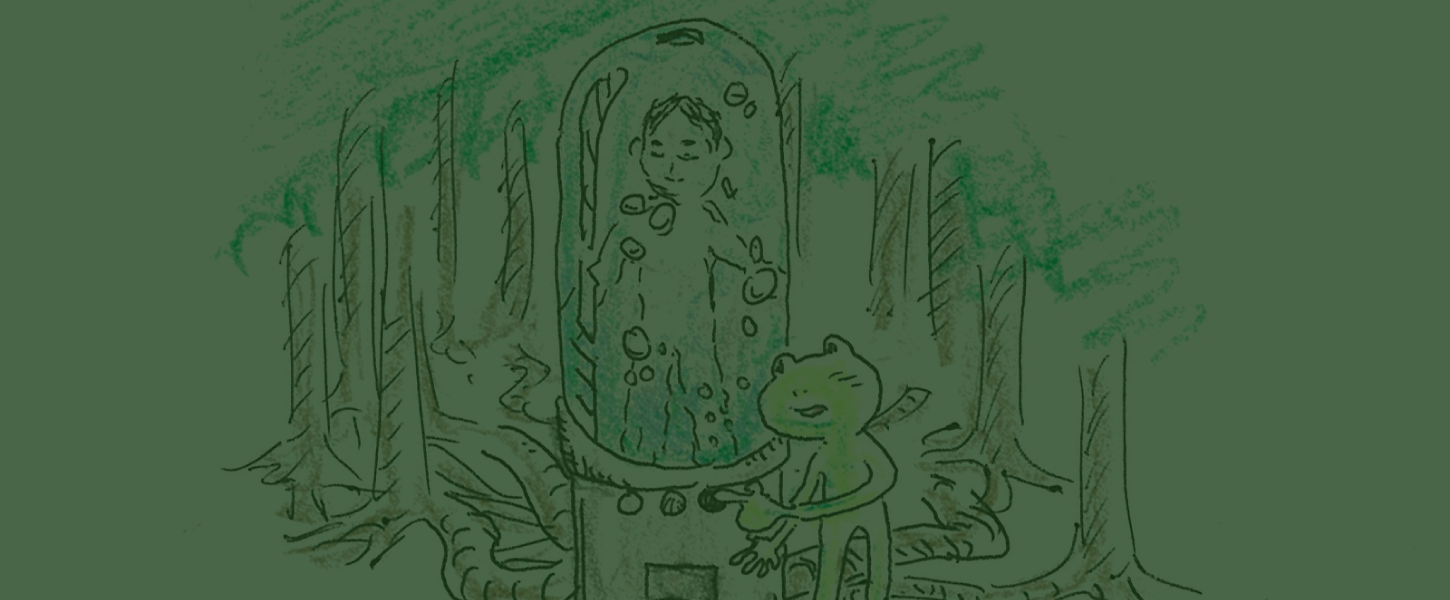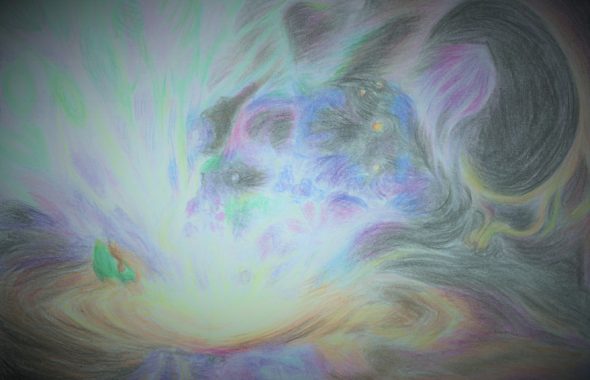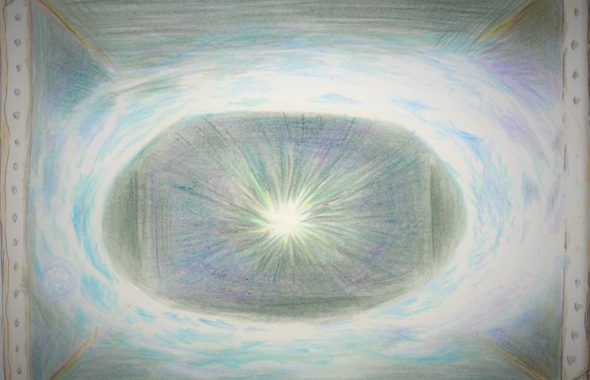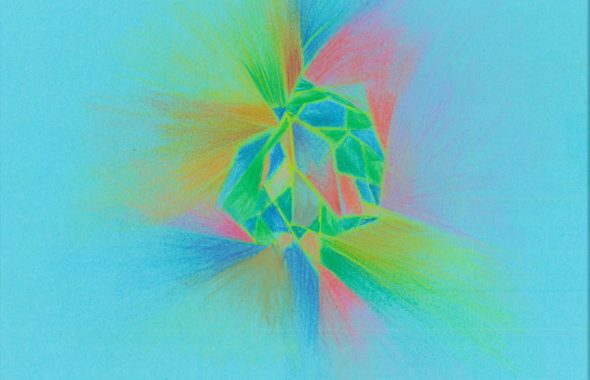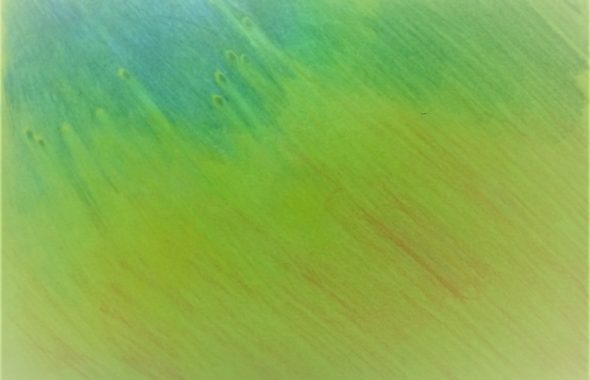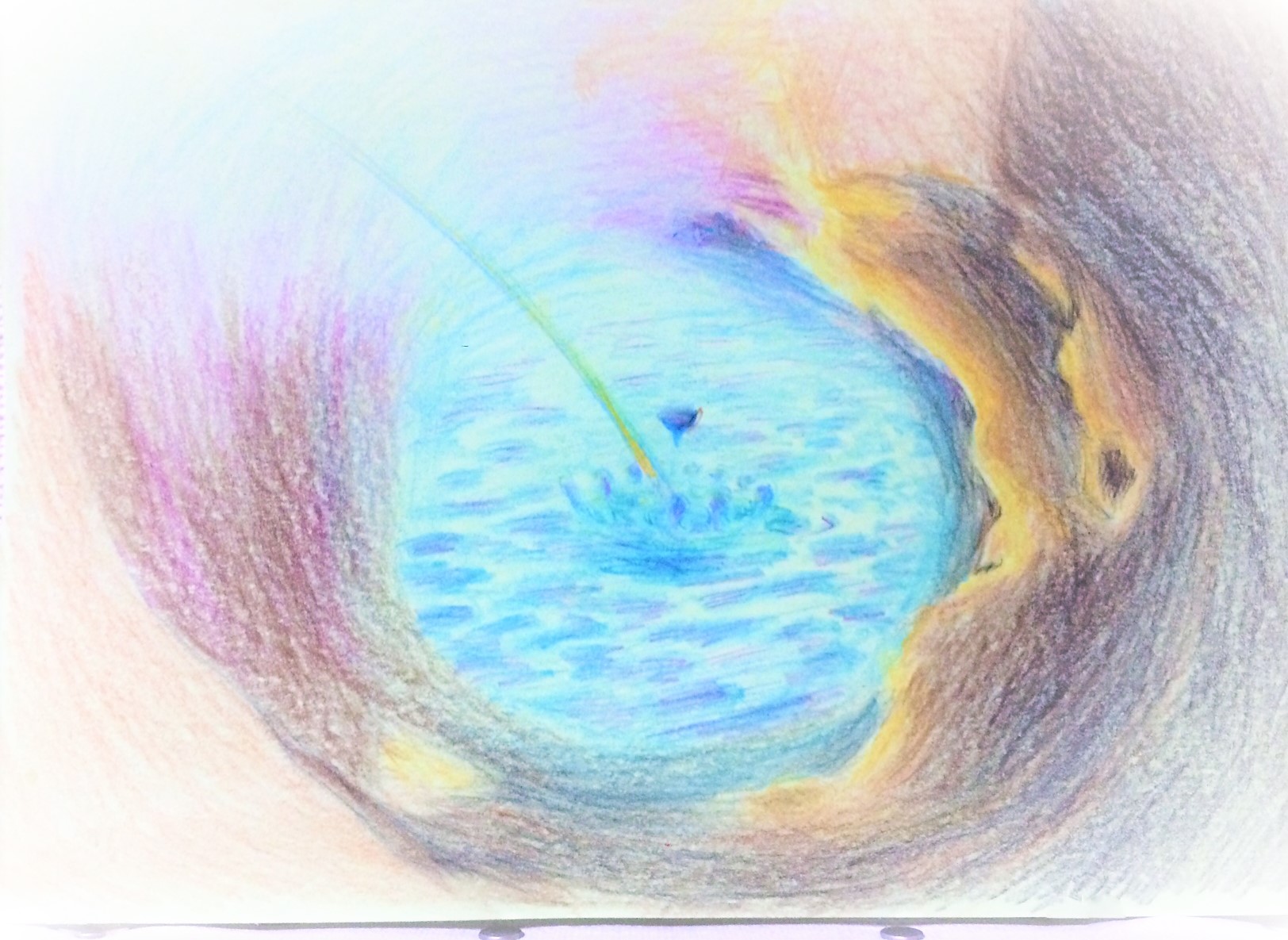
〖エピローグ〗
師のアトリエに缶詰になって絵を描き続けている間に、僕の体力はだいぶ落ちたようだった。少し動くだけでも、窮屈なからだに閉じ込められた心臓が元気に胸の内からノックした。
必要な食料品を買い込んで数週間籠っては、足りなくなった品物を外に買いに出てまたすぐ戻りアトリエに籠るという生活には肉体の活躍の場はなかった。ただそうした僕の暮し方はまるで祖父が森に籠って夢見をしていたのにそっくりだ。そう思ってなんだかとても可笑しく、そして嬉しかった。
不肖の弟子、かどうかも分からない僕にアトリエの片づけを任せてくれた師の親類の方々には状況報告をさせてもらって鍵を返した。
僕の描いた4枚の絵は、そのままアトリエに残してきた。あの家と共に処分されても構わないと思っている。もう必要のない「扉」だから。
僕は僕を連れてこちらに還ってきた。
この事実だけで十分だ。
最寄りの駅に行くと、とても懐かしい行先が案内版に表示されていた。
それを見ただけで僕はなんだかとても幸せな気持ちになれた。
その電車に乗ろうと待っていると、ほどなくして、ホームの少し奥に、階下へ降りるエスカレーターを見つけた。普段は気づかなかったそのエスカレーターを降りた先が、先ほどの行先の電車が入ってくるホームだった。それに気づくと急いで下へ降りた。と同時に電車が入ってきた。そのタイミングの良さがまた気持ち良かった。
僕は電車に乗り込み、懐かしい場所へと帰っていく。あるいは運ばれていく。これは始まりかも知れない、そう思った。懐かしいその場所へ立ち、人生の一歩を歩み出していくことのプロローグなのかもしれない。
不思議な世界に迷い込み、やっと出口が見つかった安堵感を味わいながら、新たな世界の日常に足を踏み入れることを思い描き、僕は自分に言い聞かせるようにつぶやいた、「これはただの始まりに過ぎない」と。
あの時のように駅からの道を歩いている。季節を感じる風が吹き、桜並木の桃色絨毯を作っている花びら一枚一枚がそれぞれ風に遊んで舞い踊る。この季節が来るといつも、僕はまるで自分のための季節とでもいうように、全身で桜花の優しさを謳歌するのだ。衣替えしそびれた僕の暗く老いぼれたコートに、可愛いピンクの花びらが降り注ぐ様子は、向こうの小高い丘の上にある祖父のいた老人ホームの窓から望んだとしたら、そのコントラストが老いを祝福する慈悲の雨とでも思えて、勇気づけられることだろう、そんなことを思った。
僕は自分の変化の遅れに笑った。きっと自分だけだろう、こんな時間の止まったような奴は。そういって辺りを見回した。若い女性たちの身にまとう衣服は桜並木と調和したパステルカラーで、僕の目に優しく届いた。
そんな中ふと視界に自分と同じ時間の静止を感じる要素がひっかかった。けれどもそれが何だったのか見つからなかった。しかたなく歩き進みながらやはり背後にそれを感じた。
私が振り返らないときにだけそれは姿を現している―――
僕は背中に小さな自分自身を感じながら、その彼とともに老人ホームまで続くピンクのトンネルを抜けていった。
*
老人ホームを含む街の遠くに森と山が見える。
その森へと続く山道で一台の車が止まっている。
車の脇には二人の男が立って話をしている。
そういえば最近、空気圧を測ったことがなかった、そう一人の男が言った。もう一人の男は車の下を覗き込み、パンクしたタイヤをしみじみ眺めていた。舗装されていない道に分け入り、しばらく進んできての出来事だった。
替えのタイヤもなく、電波の入らない自動車電話を見つめて困った顔をしていた男に、タイヤから彼の顔に目を移した男が言った。とりあえず歩こう。
なんの論理性もないがなぜか説得力だけはあったその言葉に押されて、二人は引き返すのではなく、山道をさらに奥へと進んで行った。その先には一つの目的地があった。夢見の小屋、そう世間で呼ばれているログハウスがこの山奥の森の中にあるというのだ。そしてそこに行けば、自分の夢が分かり、分かるから当然現実のものとなる、つまり叶うというのだ。これまでも、真理を探究する者や科学者、作家、アーティストと呼ばれる人々がそこを目指してこの森に入っていった。
けれども何も起きずに、ある者は怒り、ある者は森の中でひたすら迷い、またある者はあきらめて森を後にしたという。
*
春になって唐突に小春が帰ってきた。
「君は一体どこまで行って来たんだい?」
「土星の輪の真ん中あたりまで。冗談よ。いや、心理的な距離は本当にその位まで行ってきたのよ」そう言った小春の声が耳から僕の頭の中を通過して、僕の目の前の中空に像を浮かべた。それを見ながら話の続きを聞いた。
「君は、そんな遠くまで行って何をしてきたの?」
「何かをしに行ってきたわけではないのよ。多くの道のりを歩いたということに意味があると思うの」
僕は、土星の輪の上を左回りに歩いている彼女の姿を見ていた。
「そしてそれだけ、出発地点から遠くまで離れたということに意味があるの」
目の前の中空に浮かんだ土星の輪の上を一周して、元の地点に戻って来た彼女を見ながら言った、
「僕は今君と同じところにいるように見えて、実は周回遅れなのかもしれない」
「うん、なるほどね。でもそれはあなたが考えているようなことじゃない。もっと見えにくくて繊細なことなの。あなたといるとね、ときどき私一人になっていることがあったの。比喩ではなくて実際に。そんな奇妙なことがあるわけないと思うかもしれないけど、本当なので仕方がないの。分かって」
僕は自分の手が透き通っていないことを確かめながら言った。
「いや、分かるよ。ごめん、本当に消えてしまっていたんだと思う」
「謝らなくてもいいの。でもね、私どうしていいか分からなかった。本当に土星にまで探しに行こうかしらって思うくらい、あなたの存在が遠くへ行ってしまっているように感じたの。それだけは分かってね」
返事の言葉は何も見つからず、僕はただ一度だけうなずいた。
*
小春が戻って来てから、僕の世界の時間はとても静かに流れている。桜は満開の時期が過ぎ、残っている花びらもここのところの長雨でほぼ散った。
本当に長い長い雨だ。かれこれ二週間は降っている。小さな庭先に出来た水たまりが日に日に大きくなっている。何日目かには玄関先まで水たまりが出来ていた。
僕は玄関に立ち、水の中をしばらくの間のぞき込んだ。水滴で生まれる波紋が幾重にも広がり、その輪たちはあちらこちらで重なり響きあった。その上に映り込んだ僕の顔はいくつにも分かれては結びつき、また崩れては合わさった。
軒下から空を見上げた。何千本もの雨の線が空を覆っていた。その向こうに雲があり、さらにその向こうに太陽があるはずだが、僕からは見えなかった。ただこの地上で、雨音だけが確かに存在した。
こんな長い長い雨のある日が以前にもあったのをふと思い出した。
赤い傘の下、彼女と相合傘をしているまわりは全て雨だった。右も左も前も後ろも上も下も全て雨だった。赤い傘下に、彼女とただ二人だけの世界だった。
そのとき僕はこう言ったのだった。
「死が二人を分かつまでは、僕はこの雨降る世界の中、僕らのために傘をさし続けるからね」
のぞき込んだ水たまりに映る自分に向かってもう一度僕はそう言った。
*
かたちを変えた祝福だったのかもしれない、今はそう思う。
長い年月を通して煩わされていた病がこうして今になって全ての事象に意味を与え、ここに存在するという確かさを全方位からもたらしてくれているのをつくづく味わえたから。
そうすると、「あのとき病があったから、ああしてこうして…」と過去のすべてに対して因果的つながりが整えられ、今の僕のアイデンティティは輪郭のはっきりとしたものになる。はたして、病がなかったら僕のアイデンティティは整ったのだろうか。宇宙の中の小さな命の生成の中に、核となって命の活動をまとめるものは産まれたのだろうか。
「天の導き」そのようなものが暮らしの中で当たり前のように居場所を与えられていた時から、今のようにサービスとして買うことができる時代になった現代において、病とはそれぞれの人々の生活の中にまで降ろされた、かたちを変えた祝福なのだと、僕は強く思う。
相変わらずの雨を庭先で飽きずに眺めている僕に、台所から出てきた小春が言った、
「今さらなんだけど、なんだか言うタイミングを逃してたこと、言っていい?」
「うん。何かな?」
「えっとね。おかえり」
全身の力がふっと緩んだ。「うん。ただいま」
(完)