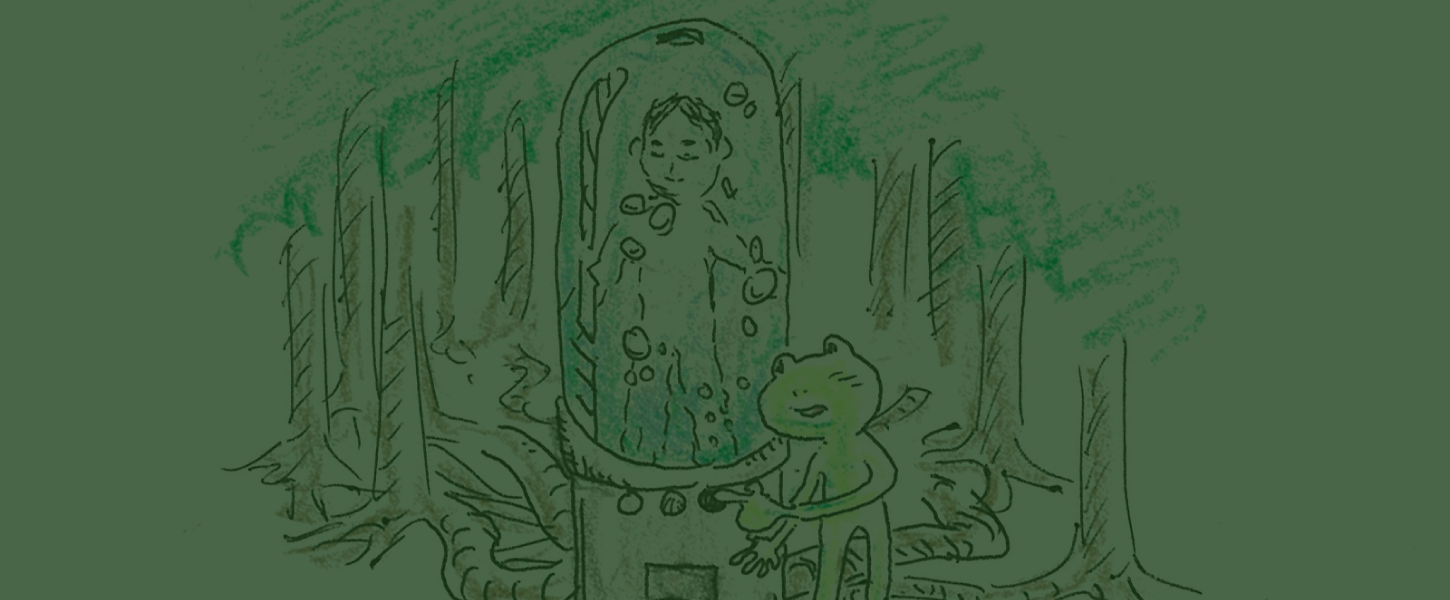〖第8話〗
祖父母に聞き書きをしていた高校生当時、私は取材もかねて広島を訪ねた。3年生に入る手前の春休みということもあり、桜がそろそろ五分咲きといったところだった。訪れた一番の動機は、呉の港に入港した戦艦大和を想像したかったということだったが、一人で原爆ドームや平和記念公園を訪ね歩きたかったこともあった。修学旅行の行き先は広島だったけれども、みんなして行くものではない、それが当時の私が強く硬く持っていた信念だった。とても子供らしい、純粋なそれに、今の私は若干、気恥ずかしさを憶えるけれど。
そんな、誰に頼まれた訳でもない現地取材をした記者気取りもあっただろう私の心の熱はどこから来ていたんだろう。きっと周りのアメリカナイズドされた同じティーンエイジャーたちの振る舞いが、すごく「上っ面」に感じて、それへの抵抗が摩擦熱を作っていたのかもしれない。広島滞在時に見つけたなんとも趣のある喫茶店に通い、書き物をしていた私に向かって、常連さんらしい方が言った言葉は、当時のそんな私にとっては火に油を注いでくれたのを思い出す。
「そんなに細かく家族の見聞きしたことを調べて、お前さんになんの得があるってんだ?人間って、そんなに厳密なものか?」
――そう、厳密なんだよ!まるで曼荼羅のように。そして、だから美しいんだよ、その宇宙の精巧さが!
当時の私が口に出して言い返せなかった代弁を、今の私が天井に向かって言っていた。
その発言が曼陀羅というジグソーパズルの最後のピースをはめたように感じ、そのあとにふと、こんなことを思った。
あれ、もしかして弟って、大和と共に沈んだ最初のおじいちゃん?
*
「ねぇ、アイリさん。」
土星の輪のカウンターの中から、ホールでテーブルセッティングしているアイリさんに話しかけた。
「私の中で男女が暮らすってことを考えようとすると必ず思い出される、というかずっと私のそばにあっては現れる記憶があるの。それは祖父が亡くなってまもなくのことでね。こちらの世界からいなくなった祖父だけれど、彼から戦争の体験を2年という時を使って少しずつ少しずつ受け取っては、私の手の中で紡いだり巻き取ったりしながら過ごした相手なものだからね、息をひきとってこの世から姿を消したとしても、私にはありありとその存在感が残っていた。だから、別れの儀式としてのお葬式には全くなじめない私が当時そこにいてね。」
「うん。」
テーブルからテーブルへとセッティングを済ませて行きながら、私の話もまるでしかるべきところに配置してくれているような感覚を憶えながら、安心感が増した中で話を続けた。
「葬儀の終了後の廊下を直会の席へと歩いているときに、参列者のおしゃべりの中から私の耳に、揶揄するニュアンスと共に言葉が届いたの。『お葬式が派手なんだって。』」
「ふぅーん。お葬式って、派手じゃいけないの?」
「あはは。私もそのとき同じことをつぶやいたの、お葬式って派手じゃいけないのかなぁ…て。その言葉に対して横にいた母はやや感情を押し殺したように言ったわ。『おばあちゃん方のお葬式が普通じゃないからって、あんなふうに、こそこそ言わなくてもいいものだけど…。』」
「小春ちゃんは、そのとき身の置きどころ、いや血の置きどころって感じだね。それが見いだせなかったのかもねぇ。そしてそれがそのまま、男女で暮らすときの自分の身の置きどころを見失っちゃうことと結びついてるのかもしれないね。」
しっくりくる言葉を、必要最小限に、そっと置いてくれるように話すアイリさんに、私はいつもながらに好意をいだいて言った。
「突然なんだけど、言っちゃいます。アイリさん、好きです!」
「あははははhhh!」
大笑いするアイリさんの笑顔にもただ引き込まれるように魅入っている私に応えるように続けた。
「はhh…同性に告白されるって、私けっこう多いのよ。ありがとね。とても嬉しいよ、小春ちゃん。」
勢いで言っておきながら、急に照れくさくなってる自分のみっともなさにさらに恥ずかしくなって固まってしまってる私を見かねて、アイリさんはさっきの話の続きに水先を向けてくれた、小春ちゃんのお母さんはどうだったの?
「あ、はい! 私が高校生のときこんなこと言われたの憶えてます。あれ、なんか急に敬語だ、私。あはは…。母と父は〝第2の新婚旅行〟という名目で熱海に2泊3日で出かけていったの。そのとき母は思春期まっただ中の私に『これまでの夫婦生活は、因縁の解消のためにお互い出会って時間を共にしていたようなものだったんだなって思うのよ。』って言った。その仕事もやっと終わったってこと? そう聞く私に『そういうこと。ようやくお互い空っぽどうしになったから、これから本当の意味で二人の生活を創っていくってわけね。』そういつになく少女のような清々しさで母は言ったの。なんかその時は、あっずるい、一人で先に抜けて、そう思っちゃったな。」
「そっかぁ、でもやっぱりそこは一人一人で向き合わなきゃならないところなんだろうねぇ。」
「そうですよね。母がすっきりしても私は私だなって。むしろ突きつけられたというか。その留守番の間もね、台所仕事をしながらそんな少女のような母の表情を思い出しつつ、代わりの夕食支度をしていたらね。玄関の開く音がして、階段を上がっていく弟の足音が聞こえたから、『おかえり!』って投げるように声かけたんだけど彼からの返事はなくってね。当時の弟とは、夫婦で言えば倦怠期のようだった。その昔、楽しく肩を並べてテレビに向かい、ウルトラマンを観ていた頃はどうやって話していたんだっけなぁって悩んでた。おかしいね。でもそっか、今思うと、侵略してくる怪獣から人類を守ってくれてたウルトラマンとともに心の中で弟と二人で共闘してたのかもね。」
サラダ用に葉をちぎりながら、そんな考えに思い至った。
夜、部屋に戻ってからまた昼間の話をふり返った。ここ最近は、土星の輪でアイリさんに肯定も否定もなく、ただただ話を聴いてもらい、記憶や気持ちが整理されて帰ってきては、その時話した内容の出来事を再度丁寧に自分の記憶のテーブルに載せ、ありのままに味わうことをしている。そのときアイリさんの気持ちの残り香があるせいか、思い出した出来事をあまり判断しないで眺められた。
寝そべって天井の木目を見つめていると、弟のことで思い浮かぶシーンが心の映写機から映し出された。
*
「弟は最近、寝てばかりいる。」
夕食の準備を母と一緒にしながら台所で私は言った。母は決して顔には出さずに私の言葉の続きがあるのかないのかを、間をとって手だけ動かしていた。私は続けた。
「第2の新婚旅行から帰ってきたらお父さんがさ、もう〝仕事〟終わりってみたいに急変して、あっという間に死んで、それから弟はすっかり変わってしまった。それまでのあの子ったらまるで生き急いでいるみたいに動き回っていたでしょ。それがさ、なんか弟の身代わりにお父さんが死んだかのように受け取っちゃって、そしたらまるで終わりが先延ばしにされて命を持て余したように、ただただ眠ってるように見えるのよ。」
母は急に凪いだように存在感が静まり、波紋が広がるように言葉を発した。
「なんかね、似てるのよ。あなたのお父さんに。お父さんも一時期ずっと床に臥せっていたことがあってね。」
母は初めて私に話す内容を丁寧に続けた。
「色んな病院で診てもらったんだけど、どこに行っても治らなかったの。それで駄目もとで私の母のところに行って下さいってお願いしたの。拝み屋の母のところね。お父さん、そういうの、全く信用していなかったからね、最初は全然聞きうけなかったわね。」
「もうお父さんの意識もなくなりかけて、許可を要することなく拝みが実現したんだよね。」
正解というように頷いた母に向かって言った。
「お母さんのおなかの中にいるときに肌でみていた。その時のイメージは頭に浮かぶの、今でも。」
私も心の水面を出来るだけ静かにさせて答えた。そして少し居心地の悪さを感じて、それが、まだ自分の血の置きどころの悪さから来ていることだけを確認した。
母は嬉しい気持ちを顔ににじませて頷いていた。
母とはある時から戦場の同志のような仲でもあった。
戦場とは我が家だった。そこでは私も、母と同じく今一つぱっとしない何かに曇っていた。その曇りは家を出ると少しは薄らいだ。けれども同様の曇りが外にも存在した。そうか、この社会全体に広がっているもやのようなものが、家ではより結晶化されて強く感じるんだ、そう私は思った。この曇りは、私という日本人が抱えているものなんだ。この国のどこに行ってもきっと変わらない。
もちろん行ってみないと本当のところは分からない。けれども私はそこに留まろうと思った。ここで私をこれまで育ててくれた母と曇りの取れた幸せな時間を過ごしたい、そう決心した。
そのことは、弟との和解をももたらすように感じた。この家がこれまで背負ってきた〝男性の生贄の上に平和を得る〟とでもいった神話的な呪縛が、女と男であるというだけで弟との関係性を破壊的に難しくしてしまっているそこから解き放たれるように感じた。いや、願った。
この円い世界の無数にある中心のひとつから、私は丁寧に私の世界を紡いでいくこととなった。
続いて祖父母が心の映写機から映し出された。
祖母は向き合って座っている高校生の私に語りかけた。
「私はね、8月15日の天皇陛下のお言葉をずっと考えてきました。あなたのお母さんを育てるときも、おじいさんを看病していたときも、拝み屋として、様々な人の生活の中での悩みを伺っていたときも。」
私の中での祖母の印象は、彼女の言ったこのセリフに尽きる。なんて分かりやすいスジを持った人なんだろうなというのが、彼女への私からの最高の評価であり尊敬の想いだった。着物をまとった姿しか見たことのない彼女の佇まいは、それだけで天地に一本のしっかりとした軸を通して、それに寄りかかって力まずに立っているなぁ、そんなふうに私は特に知識も意味もなく、イメージだけでそう思ったものだ。
そんな祖母に比べると、母はどこか透明なところがあった。祖母ゆずりのびっくりするくらいにサイキックな才能を、子供たちが自由に育つようなイエ作りにすべて注ぎ込んでくれた人だった。
天井から私の物思いが一段落するのを確認したかのように、祖母は床にいる今の私に口を開いた。
「私は結局思いました。天皇陛下のご威光と、原子爆弾の閃光は一緒のものだったんだと。私たちはいずれの光にもやられてしまったのですね。」
私も祖母の言葉に自然と口を開いた。
「天皇陛下万歳と言って死んでいった日本人たちも、そのご威光の犠牲になったとみるってこと? 彼らは本望だったのではなくって?」
「もちろん一人一人の心に土足で踏み込み断定するような失礼は決していたしません。そうではなく、ご威光も原爆の閃光も、私たちの外からやってきた大きな光だったのだということです。その両方の光が、兵隊さんや普通の生活者たちに降り注ぎ、英霊として小さく小さく粉々にして消し去ってしまったという事実において一緒だと思い至ったのです。」
「ねぇ、おばあちゃん。私にとってはこうして目から鱗がいっぱい落ちる話を教授してくれる、おばあちゃんこそ光だよ。」
そう言う私に笑みを浮かべて祖母は応えた。
「えぇえぇ。でもねぇ。あなたに何かを教えてくれるのは、あなた自身の魂よ、小春。それが発してくれる光をこそ、大事になさい。」
祖母は透明度を増していき、反対に祖母の横で話を聴いていた祖父が光の度合いを下げるようにして透明度を落とし、形を顕して私の目に入った。祖父は布団で寝ていてその枕元から高校生の私が語りかけているようだった。
祖父の昔語りのあとに、まったく突然に小春は言った…
(第8話/全10話)