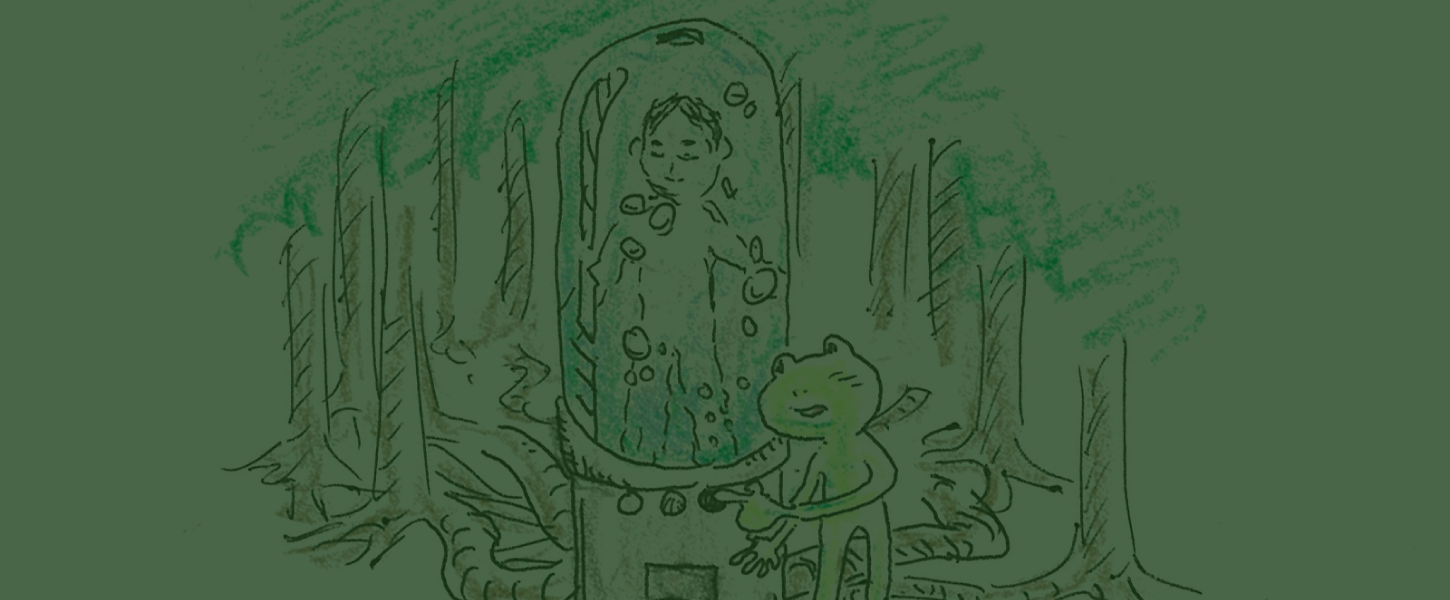〖第7話〗
部屋に戻ってなかば放心したまま、今日は敷きっぱなしで出たふとんに潜り込んだ。そして私の中から自然と浮かんできた記憶を、また天井を見ながら追った。
大学時代の私は、香りに対してとても敏感だった。五感というものが何にもまして私の世界を創っていく足がかりだと悟った高校生の終わりから、私の中の五感は解禁されたかのように生き生きと表舞台に出てきて世界を創りだした。その感覚の中でも特に匂いが当時の私を作っていった。そうした五感たちとの関係性がまだうまく作れていなかった当時の私には、彼らに振り回されることも多々あった。
都心に大学があったので、私も満員電車での通学を毎日のこととした。人が毎朝そうやって中心部へと集まっていくことで、独特な匂いが発生するのを日々味わいながら通っていた。その集まって生まれた匂いは、まるで一つの星座のように感じられた。目に光が届く星、届かない星、それらが無数に散らばる宇宙空間で、見えている星どおしを平面的につなぐことで星座という像を浮かび上がらせるように、重層的に存在する個々の人々の匂いが私の立っている場所から一つの像を結ぶ。そんな風にして街のあるところで我が家の生活の匂いが伝わってきたりするものだから、私は今どこにいるのかと揺れた時期もあった。
*
今また匂いを意識していたら、船の金属の匂いが伝わってきた。
あれ、ここはどこだろう? 夢を見てる? そう思いながら私は歩いていた。
しばらくするとクルーザーの上から海原を見ている視界が広がり、この場面転換の速さはやはり夢の中なんだわと思った。
甲板に一人、とても見覚えのある人が立っていた。
弟だった。
空は快晴で青一色だった。周囲すべて海の青が囲んでいて、天も地もそれこそ青一色の世界を艦は進んでいった。
私の中に弟の想いが共鳴するようにして聴こえてきた。
〈静かだ。つくづく静かだ。僕の心が静かだ。驚くほど静かだ。人が死を覚悟した時は、こうも心が静まるのか。人間って簡単だなぁ。世間の波の中で右も左も分からなくなってしまって、人間とはなんと複雑で面倒なものなんだろうかと、そう思っていた僕はどこに行ったのだろう。
しがらみとは人と人をつなぐ糸のようなもの。それがあって生かされもしているが、それぞれが我が我がと願いをその糸の先に投げかけてしまうとあちらこちらで糸は引き合いこんがらがってしまうんだろう。こうして死を覚悟してみると、何ものにも期待せず、糸を持った手を放せるのだ。すると世界はこんなにも簡単になって静まってくる。戦場に立ってようやくそれに気づくなんて僕はつくづく阿呆だ。〉
そして場面がまたすっと転換した。
舟の先の方に一つの見覚えのある島が近づいてきた。いつどこで知ったんだっけかな、そう考える一瞬の後に、祖父の戦争体験のインタビューをさせてもらった時に色々見た資料のそのページが頭の中に開いて現れた。
次に意識の枠に入ってきたのは建物の中の場面。私はそこでは男性で、立っている位置から左右前方へテーブルが並んでいた。左右のテーブルに挟まれた中央のスペースを前へと進んで行きながら、左右三グループずつ、計六グループの人たちが座っていて挨拶を交わした。
その中には少し前の、私と同じ顔と記憶を持つ人に違いない者もいた。今は確かに他人だと分かるけれど、その人はどう思ってみても私の知っている私だった。でも今の、男である私の方が今は確かに『私』だった。
私の知っている私が言った。
「本当の絶望に至るのは簡単です。負け戦を続ければいいのですから。」
続いて、男である今の私が言った。
「国力に大差のある相手に勝つためには、我々は全く新しい戦い方を生み出さなければならなかった。そして行きついたのが神風特攻だった。それは戦争序盤の我々を優位に立たせた。我が国には目に見える神がいたから、そのご威光を授かれば誰であれ神風を吹かす神兵となれた。多くの戦地へと拡大していったその神兵たちは、地上世界のモノの力を持つ相手に優位に立ち、勝ち進んでいけた。けれども相手は我々の神風を理解し、より地上的な神を生み出してしまったのだ。それはきっと我々が示した神風の脅威が直感となってしまったのかもしれない。原爆という地上をものすごい光に包む魔の神が我々を圧倒した。」
「再び言います、本当の絶望に至るのは簡単です。戦力に大差のある戦を続ければいいのですから。神風を模倣し、それを超えた神光を産み出した相手ならなおのことです。」
私の知っている私はそう繰り返した。
右奥からついさきほど聞き覚えのある声が響いた。
顔を向けると弟だった。なぜか彼の周りだけ船内に見えるその場所で、独り言のように弟はつぶやいた。
「この僕の頭の上にいる三千もの神兵に想像の目を伸ばし、一人一人の姿を思い浮かべながら最期のにぎり飯を結んでいった。一人に二個、大きなおむすびをこしらえた。この大和の中心部で、周りの海の見えない中、最前線でこれから散っていく彼らへの手向けの気持ちで一心にむすんだ。そのむすびはただの塩むすびだったが、中心には不思議と何かが入っているように感じられた。
艦長の声が大和全体に伝わった。それを合図に、僕よりも十も若い十代後半の青年たちは大きなおむすびを頬張った。〝死ニ方用意〟と書かれた四六ミリ砲の土台の鉄板の前では、はたしてどんな味のするものなのだろう。
この大きな大きな巨体の中で、ちっぽけな人間たちは特攻という道行きを途中下車することなく進んでいく。あきらめというのではない、何かとてつもないシンプルな道程。そう、人の行きづまりの透明な結晶だった。硬い体の大和に匹敵するほど硬い透明なダイヤのような諦観だった。」
テーブルの左奥に祖父がいた。
声にならない声で、誰にというのでもなく、彼は語りだした。
「本当に様々な出来事が現実味を失ってきている。目的の分からないこの戦争、大義名分に少しも反応しない我が心、敵味方の死傷が苦しいために感じることをどこまでも脇へやった結果の空虚感。そんな中、時々やってくるのだ、無性に確かな手ごたえのある感覚を欲する欲求が。そしてなかなかそれが得られないでいるとその欲求は私の想像の中へと入ってきて、心の中に散らばっている様々な感情や空想をあさり始めるのだ。
そして見つけるのだ、私の中にこっそり隠して自分でも忘れている残酷さを。それが何よりも現実味のある確かな手ごたえを欲求に与えた。私の想像の中では欲求に力を与えられた残酷さが数々のむごたらしい殺害場面を見せてきた。日中の肉体的な作業へ向けられていた注意が自由になった夜、そして夢の中で、私は非常に恐ろしい、手に汗握る体験をするのだ。このままではいけない。私は私の暗がりに呑み込まれ死んでしまうだろう。」
男である私は祖父の語りを聴きながらある日の午後を思い出した。
その日は静かだった。砲弾の発射される音も一切耳に届かなかった。
この第八小隊も今は、つかの間の休息を得て、みなそれぞれの作業から解放されて過ごしていた。
小隊長である私は日課の軍記を書きながら隊の仲間たちの姿を見つめた。脇のベッドで横になりながら私の様子を見つめていた代隊長と目があった。
しばしお互いの呼吸が重なる間があったのち、代隊長が口を開いた。
「みんな、暇そうにしてるけど、心の中が嵐みたいに忙しいのだよ。気が全く休まらん。呼吸も浅くてたまらんよ。」
視界の外から声が届いてきた。
「小隊長! この戦争の意味は一体どこにあるのでしょうか。私は大事な人を故郷において空襲で亡くした憤りから、ここに立つことになる選択肢を選んだのですが、そもそも敵を撃つ戦の意味は、その想いからは導き出せずにいます。敵だって私と同じような経験をし、怒りや悲しみを受けてこの戦争に足を踏み入れただけの者もいるはずです。僕らは一体何をしているのでしょうか!」
そう強く訴えてきた若い隊員の顔は祖父のそれだった。
*
夢から目が覚めてもしばし今までの体験が感覚的にすべてありありと残っている中で、高校生の私に祖父が話したワンシーンが思い出された。
「星少尉殿…。その見事な手腕、意志力はほれぼれするようだった。参謀本部は当然机上で空論するのが仕事なのだが、その高みから全体を観て論理と直観で描いた空論を、その同じ高さまで上がっていっては彼らの見ている視界を共有し、論理をなぞり理解と調整を加え、それを持って今度は再び地上に降下して来れるのだよ。そして前線の一小隊の小隊長としてマネジャーもして、プレイヤーもした。頭は天にも届くほど高く伸び、足は地にしっかり着いて立ち、手はその上下両方からの指令を調停して意志を持って動かしている。そんな風にわしには見えたものだ。」
「今その人はどこかで生きているの?」
高校生の私は、会ってみたいという想いを抱いて聞いた。
少し間があって祖父は応えた。
「実を言うと、行方をくらましてしまった。わしのしでかしたことを穴埋めしようとして、何か大事な機密事項を知ってしまったらしいということだけは風の便りで耳に入ってきたのだが、それ以上のことは誰も知らない。どこかに墓があるのなら、勇んでも駆けつけたいものだよ…。」
そうか、私は夢の中で星少尉だったんだ。おじいちゃんのあの切実な訴えを聴いてくれた彼になっていたんだ。
そう思ったら、私が高校の頃、一生懸命におじいちゃんの話を聴きとっていったことと重なり、自分自身が本当に星少尉にでもなったように感じた。あるいは私に彼の浮かばれない霊が憑いていたのかもしれない。そう自然に思えた。
そういう「血の仕事」だったのかもしれない。
祖父の語りの続きが思い出された。
「あの戦争が終わって数年間は自分がどこにいるのか分からなくなってしまってな。もちろん戦場でのショックということもあったし、日本中が夢遊病にでもなったかのようだった。ただそれだけではなくて、あのとき、幽霊がたくさん集まってきたんだよ。」
祖父はサラッと幽霊という言葉を使った。本人にとってそれは本当の体験だったからなんだろう。彼は続けた。
「あの戦争で生き残った者の中で少なからずの人間が、我を殺してお国のために死んでいった物言わぬ仲間たちの代弁者として彼らから選ばれたはずだ。私もその一人だった。昼夜を問わず、わしの元に訪れては妻にこれこれ伝えてくれだとか、母への感謝の想いを伝えてくれだとか忙しく言っていった。そのうち幽霊たちの訪問は徐々に数を減らしていった。三年ほどして静かになった頃、私自身が死にかけていることにようやく気づいた。あちらの世界に彼らと共に行きかけていたんだな。私の看病に来る者は皆具合を悪くしてな。その中で妻だけがずっと看病し続けてくれた。大和と共に沈んだ元夫の仇を打たんとするかのような必死さでわしを生かしてくれたのだよ。」
(第7話/全10話)